認知症対策:接し方はアイコンタクトとユマニチュード!! | ガッテン!
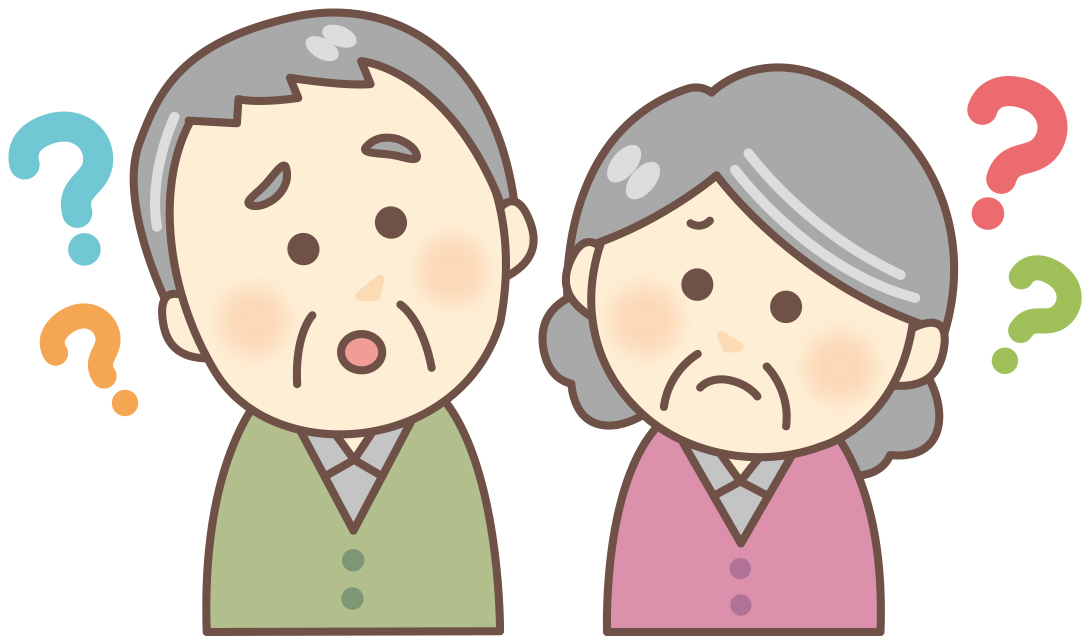
認知症患者への接し方はとても難しく、そして細心の注意が必要です。認知症患者の目線に立って接する必要があります。
現状困っている方への改善ポイントとして、大きく2つあります。「アイコンタクト」と「ユマニチュード」です。この2つの接し方で認知症患者との意思疎通が改善した事例もあります。
今回の記事が認知症介護にお役立ちいただけると幸いです。
スポンサーリンク
アイコンタクトで視線をつかむ
相手の正面に入り、視線をしっかり交わすことが大事です。
認知症患者の視野
認知症患者の視野の範囲は正常者に比べて狭いです。介護人が近くにいても気づいていないことも多々あります。
でも正面は見えています。だから、真正面ではない位置から話しかけたり、いきなり真正面の視界に入ってくることは、認知症患者を混乱させることになります。
正面からのアイコンタクトが重要
●相手の真正面に入り視線をしっかり交わすこと
●認知症患者からある程度距離を取り、真正面から近づいて患者との適正距離を測る。(近すぎて恐怖感をあおるのはNG)
●患者との目線を合わせて患者の視線をつかむ。この時Smileを心がける(無表情や沈黙は恐怖心をあおる)
※スムーズに意思疎通が取れるようになれば、症状改善の可能性もあります(暴言や歩き回るなどの症状が改善された事例あり)
ユマニチュードとは、認知症のケア技法
フランスで生まれて39年の歴史を持ち、日本の医療機関や介護施設でも普及しつつあります。フランス語で「人間らしさ」を意味します。ユマニチュードの概要と基本技術について以下の通りです。
ユマニチュードとは
知覚・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいたケア技法です。人間らしさ や 人間らしさを取り戻す という意味がこめられています。
「見る・話す・触れる・立つ」という人間の特性に働きかけ、ケアを受ける人に 自分は人間である ということを思い出させる。ケアを通じて、言葉によるコミュニケーションが難しい人とポジティブな関係を築いていき症状改善を施します。
見る
水平に目を合わせて、正面から顔を近づけて、見つめる時間を長くとるようにします。
水平な高さは「平等」、正面の位置は「正直・信頼」、近い距離は「優しさ・親密さ」、時間の長さは「友情・愛情」というポジティブなメッセージになります。
話す
ポジティブな言葉を用いて、優しいトーンで穏やかに歌うように話しかけます。返事やうなずきなどの反応がない場合は、オートフィードバックという技法を用いてみます。
オートフィードバックとは、自分の行っているケア内容を実況中継することです。たとえば「これから腕を洗いますね」「温かいタオルを持ってきました」「肩から洗いますね」「あったかくなりましたね」「気持ちいいですか」などの言葉をかけ続けます。
触れる
ポジティブな雰囲気でゆっくりと、手のひら全体で広い面積でなでるように優しく触れます。触れるときは飛行機が着陸するイメージで、手を離すときは飛行機が離陸するイメージです。患者の移動の際は必要以上の力は使わず、体のある部分を動かす時は、更に優しく力を使わないように意識する、とにかく力づくで行わないようにします。
手や顔や唇などの敏感な部位にいきなり触れると驚かせてしまうため、最初は上腕や背中などから触れる必要があります。
また、手首や足を「つかむ」とネガティブなメッセージを伝えてしまいます。ケアを行うときは無意識につかんでしまわないように注意することが必要です
立つ
立つことには、骨に荷重をかけて骨粗しょう症を防いだり、筋力の低下を防いだりするメリットがあります。
また血液循環を改善し、肺の容量を増やすこともできます。
高齢者はある日突然寝たきりになってしまう場合があります。
ケアが必要なご高齢者には、立って歩く機会を1日20分程度つくることが必要です。たとえば40秒間の立位保持が可能な方なら、40秒立っていただいている間に、清拭や洗面、歯みがき等のケアの一部を行うことができます。
近くにいすを用意して、立位や座位を組み合わせるなどの工夫も必要です。
それぞれの時間を合わせれば、20分ほど立っている時間をつくれます。
ユマニチュード(番組紹介の技法)
アイコンタクトを重視する介護法の一つが、フランス発の『ユマニチュード』。“人間らしさを取り戻す”という意味の造語で、この介護技術は世界10か国以上に広がっています。40年以上に及ぶ介護現場での経験と脳科学的な知見を取り入れ、400以上の技術を体系化。アイコンタクト以外にも、明日から実践できる技術がたくさんあります。その一部をご紹介します!
丁寧におじぎをしない
認知機能が落ちていると、自分では相手に気づいてもらっているつもりでも、実は認識されていないことがあります。まだ気づいていないのに丁寧におじぎをしても、相手には意図が伝わりません。まずは相手と視線を合わせ、コミュニケーションを始める準備をすることが大切です。
ほどよい距離感を保たない
人にはパーソナル・スペースといって心地よく感じる空間があります。一般の人にはかなり近いと感じる距離でも、認知機能が落ちた人にはそれが愛情を感じられる適切な距離であることがあります。しかし、相手がのけぞったり、後ずさったりしたら、それは近づきすぎです。相手にちょうどよい距離感を探ってみてください。
てきぱきしない
介護をする人の動きには、言葉によらないメッセージがたくさん含まれています。体を拭いたり、着替えを手伝ったりケアをするとき、てきぱきするのがいいように思えます。しかし、手早い動きが相手に伝えるメッセージは、そんなつもりはなくても「あなたを乱暴に扱っていますよ」となってしまうことがあります。これでは相手は緊張したり、怒ったりしてしまうかもしれません。丁寧にゆっくり、相手の反応を3秒くらい待つつもりで一つ一つのケアを行うことで、相手に安心感を与えてケアを受け入れてもらうことができます。
余計なことはしゃべる
ケアに集中していると、つい言葉が途切れて黙々と仕事をしてしまうことがあります。それは、相手に“自分が存在していないように扱われている”とマイナスの印象を与えかねません。そこで、何か介護するときには、いつもの3倍話しかけるくらいの意識で声をかけましょう。ポイントは、「あたたかいタオルで拭きますよ」「右腕をあげましょうね」など、実況中継のように言葉に出すことです。そして、「気持ちよいですね~」「きれいになりましたね~」など、前向きなワードを選ぶことも大切です。
間違いをなおさない
認知症により記憶力や判断能力が低下している場合、実際は80歳なのに20歳だとおっしゃったり、ずいぶん昔に退職したのに、仕事に行こうとしたりすることがあります。私たちにとっては途方も無い間違いであっても、ご本人にとっては真実のことなのです。それを否定したり怒ったりすれば、なんで自分は注意されているのか分からず混乱を招きます。ですから、状況に応じてその人の世界に飛び込んで受け入れることも、ときには重要な介護の技術です。
触れる
何か日常的な介護のとき、ついつい手をつかんでしまうことありますよね?しかし、それは、認知症の方に「自由を奪われている」「強制されている」など、悪い印象を感じさせてしまいます。触れるときは、下から支え、広い面積で触れることで、「安心して大丈夫ですよ」という言葉によらないメッセージを伝えることができます。
思い出ノート
多くの認知症の方が抱える記憶障害。しかし、記憶と一口に言っても多様な記憶の種類があり、その仕組みを介護に生かすことで、認知症の方の症状に変化が生まれることがあります。
認知症の方は新しい情報を記憶することが困難です。症状が進むと、30秒前のことも忘れてしまうと言われています。一方で、昔の記憶は覚えていることがあります。中でも『うれしかった』『楽しかった』『誇らしかった』など良い感情と結びつく記憶は長く残ります。そこで、家族旅行やデート、子供の運動会のときなど、昔の写真をまとめた『思い出ノート』を作るのも良いでしょう。感情が高ぶったり、混乱しているときなどに、一緒にノートを見てそのときの話をすることで落ち着いたり、忘れていたことがよみがえって前向きになったりと、症状に変化をもたらす可能性があります。介護する人が相手のことを深く知り、より大切に思うきっかけにもなるのでオススメです。
ごはんのお皿は一つずつ
ご家庭で起きる困った状況の一つに『ごはんを食べてくれない』があります。実はそれには理由があると考えられています。認知の機能が落ちると判断能力が低下します。その結果、食卓のどの皿を選択して良いのか分からず混乱してしまうことがあるそうです。そのときに「早く食べて!」とせかしても逆効果です。そこで、解決策としてはご紹介するのが『皿を一つずつ出す』です。目の前に一皿ずつ出すことで選ばなくて良い状況を作れば、混乱せずに食べてくれる可能性があります。また、食事の介助をする(スプーンなどで食べさせる)場合は、いきなりスプーンを口元に運ぶとビックリさせてしまうことがあります。したがって、一度スプーンを相手の目の高さまで上げて認識してもらい、「これから食べますよ」と知らせたあとで口に運んでみてください。
スポンサーリンク